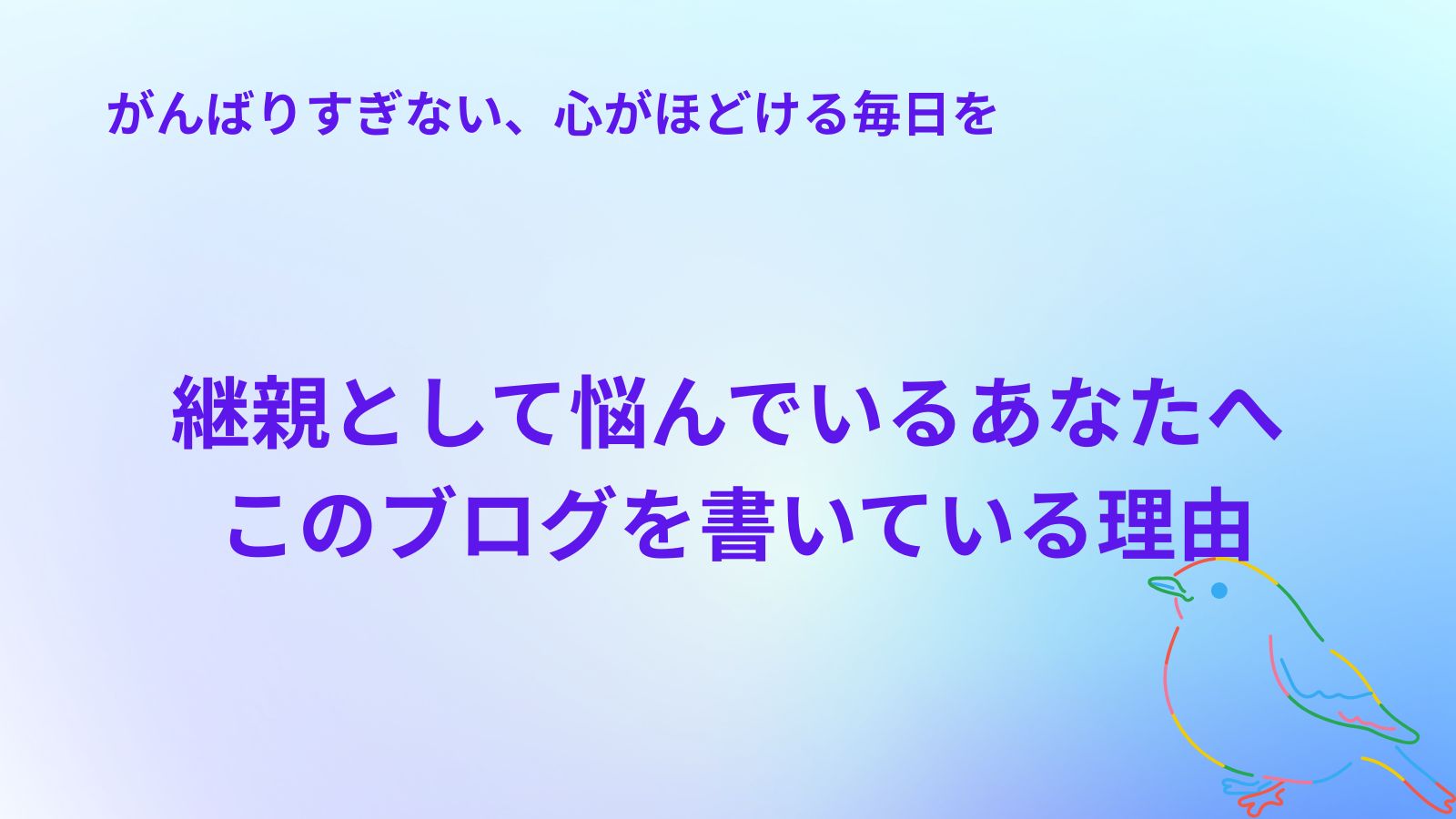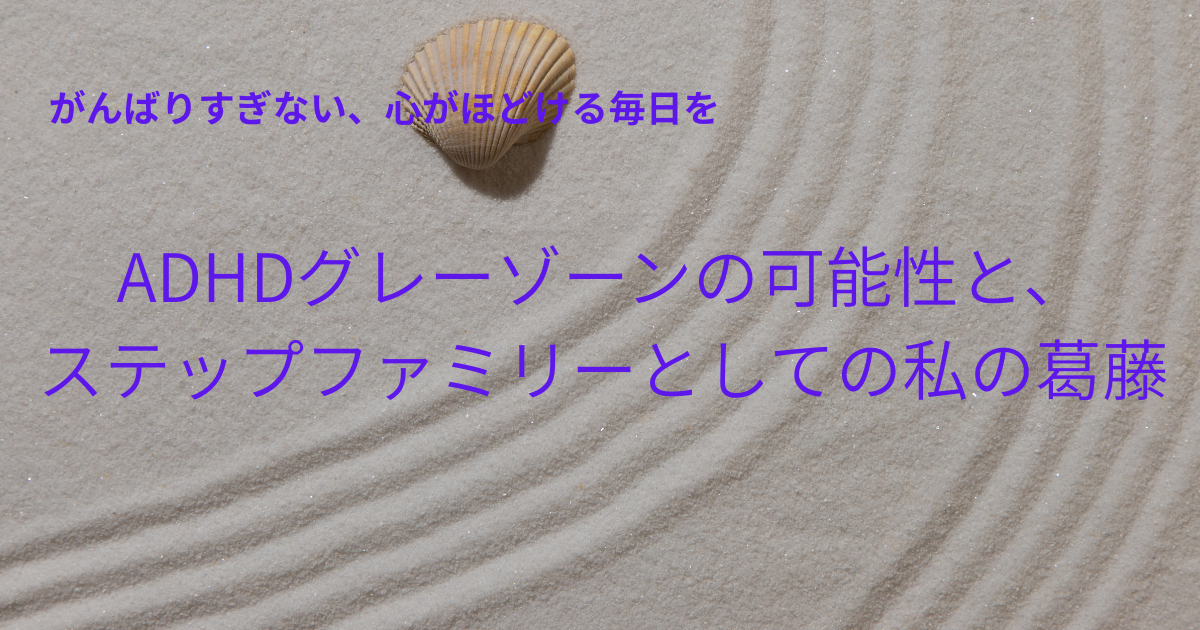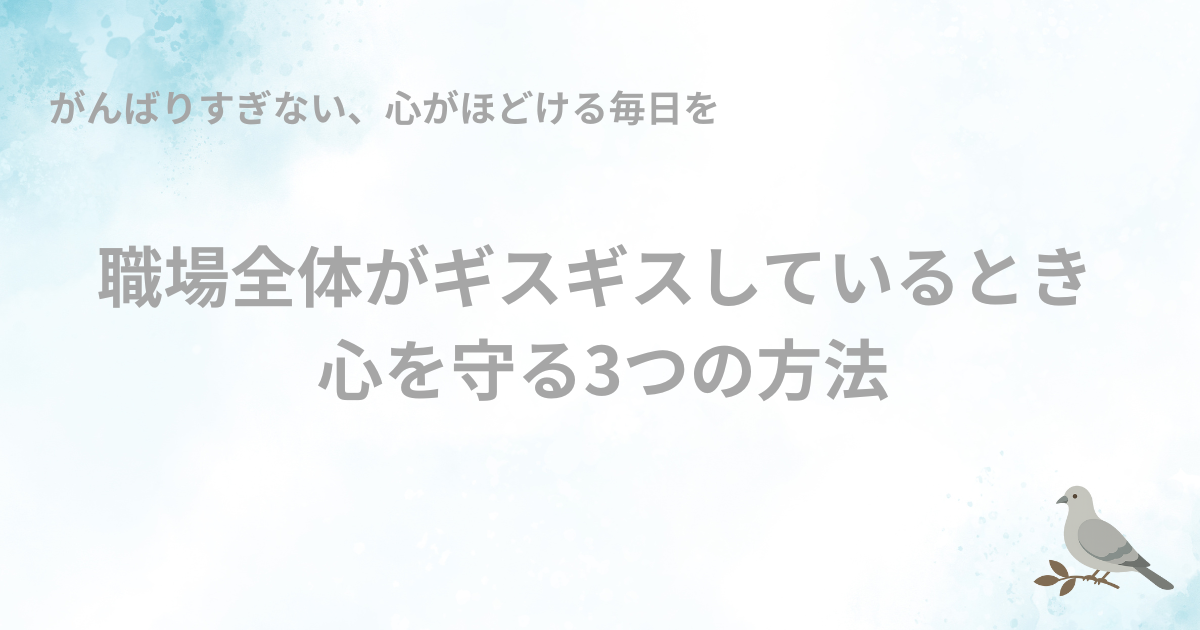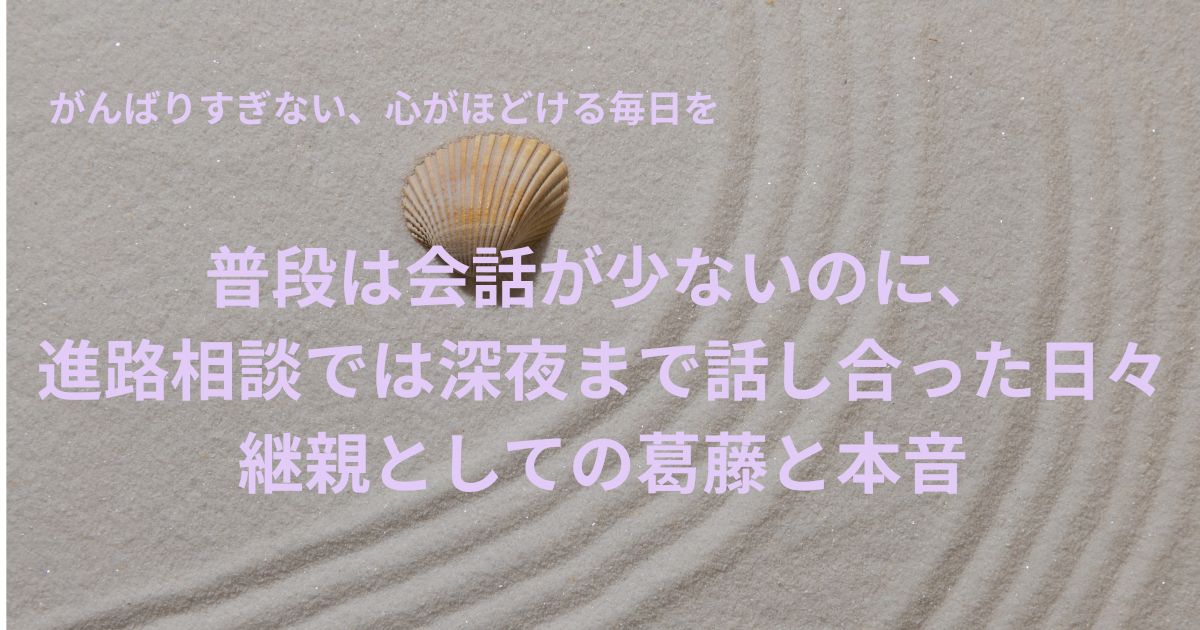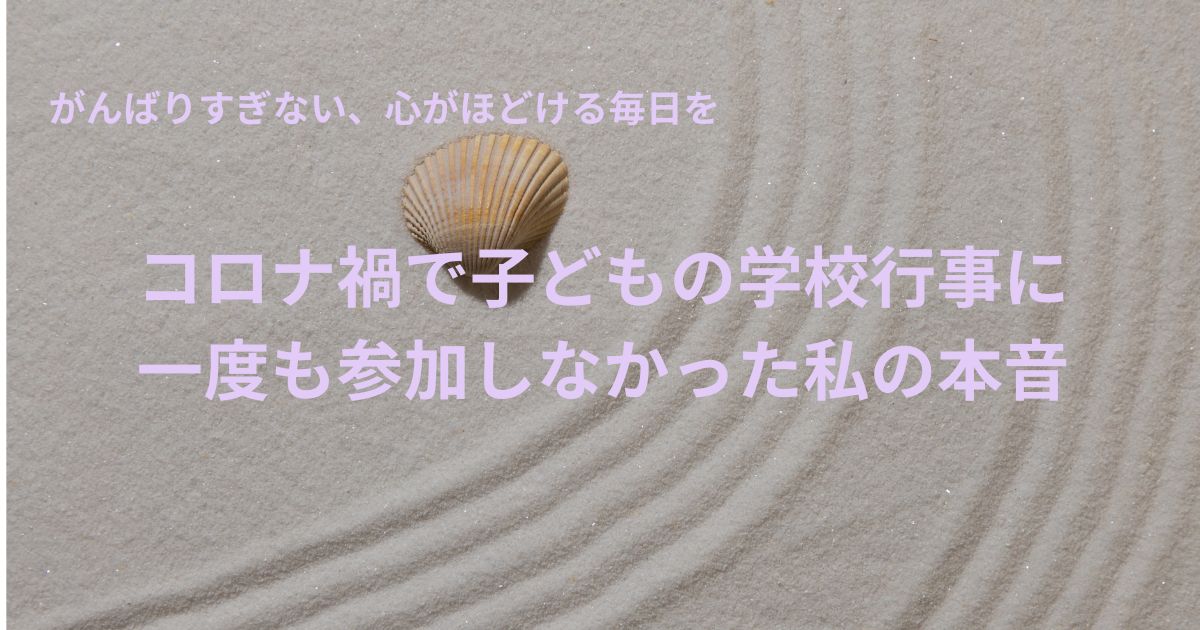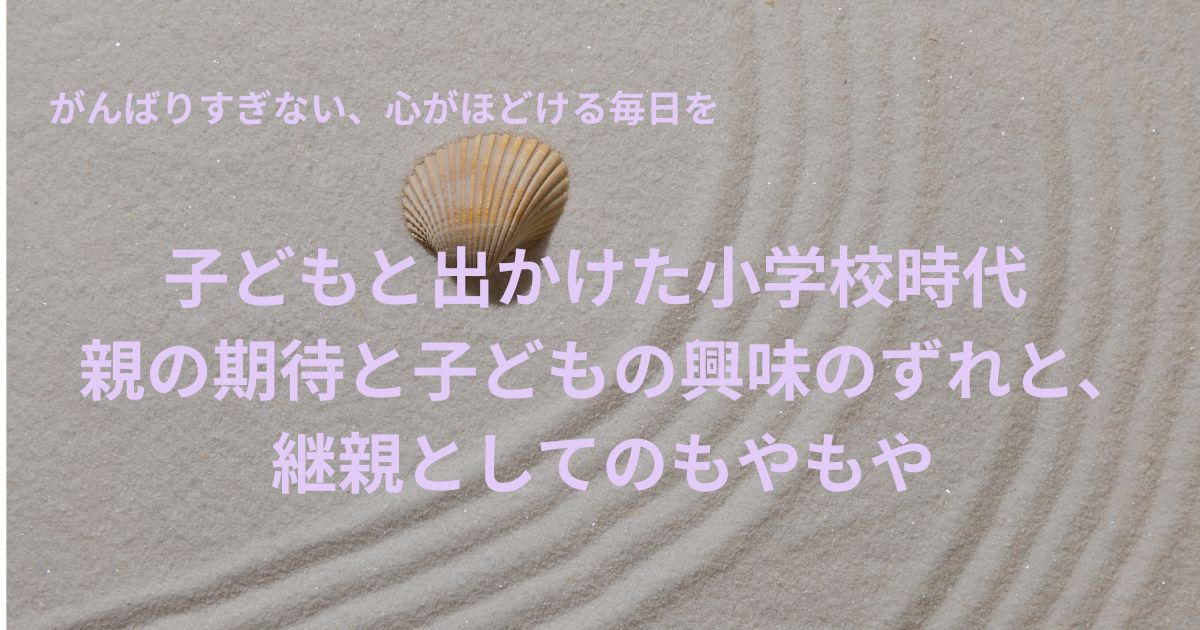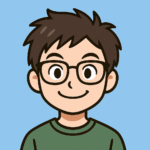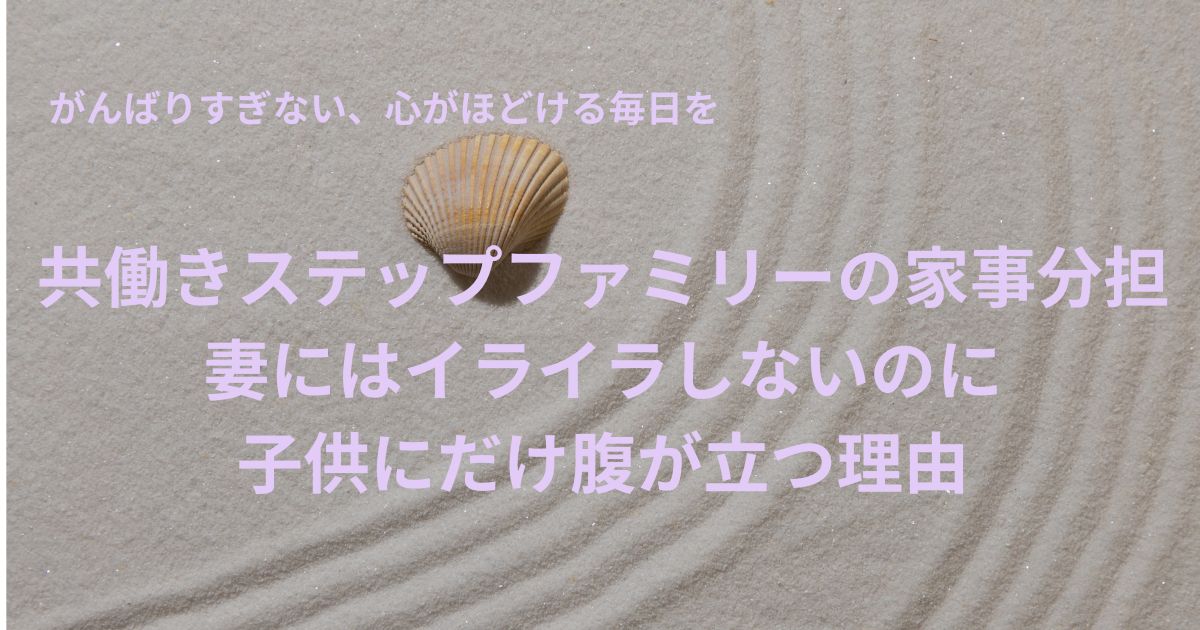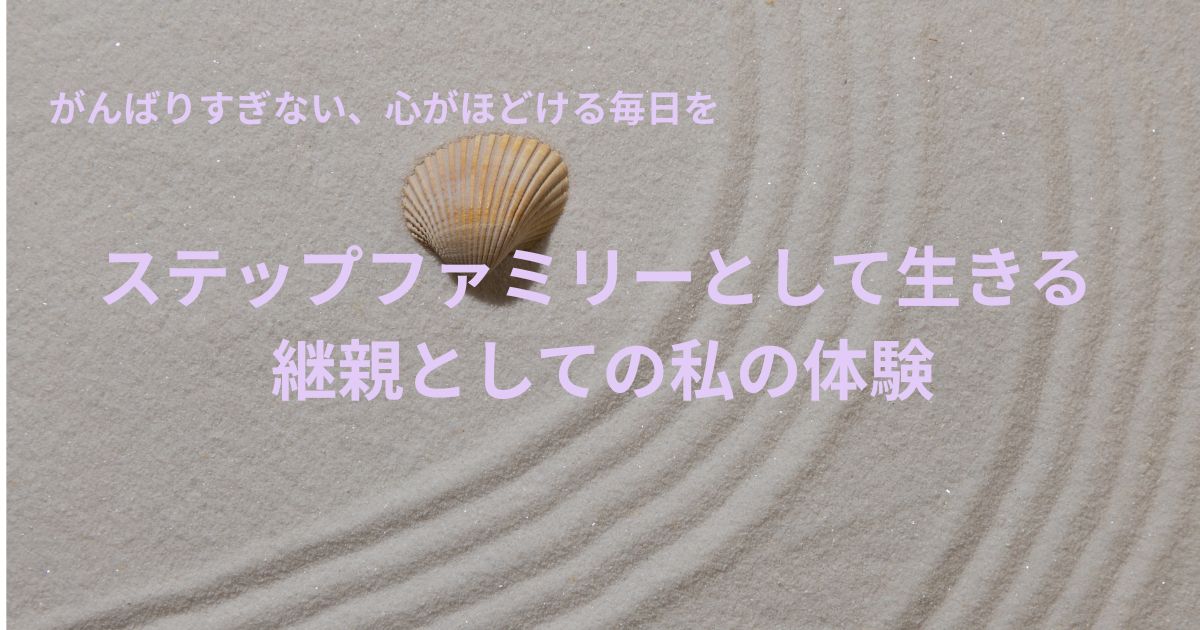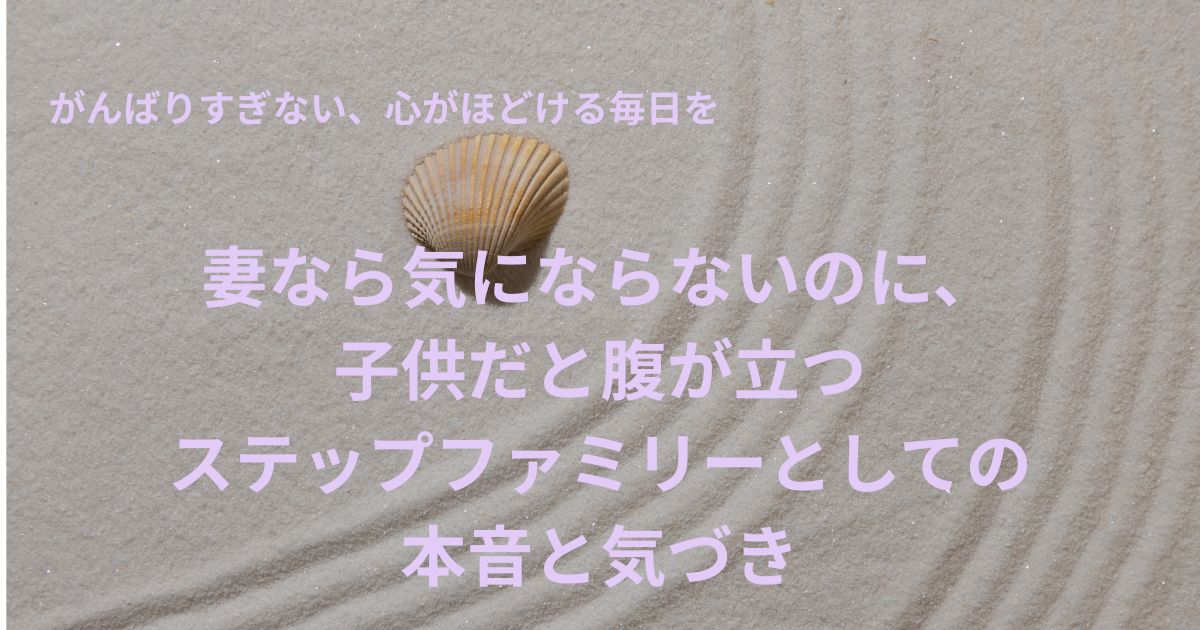進路相談では深夜まで話し合った日々 ― 継親としての葛藤と本音
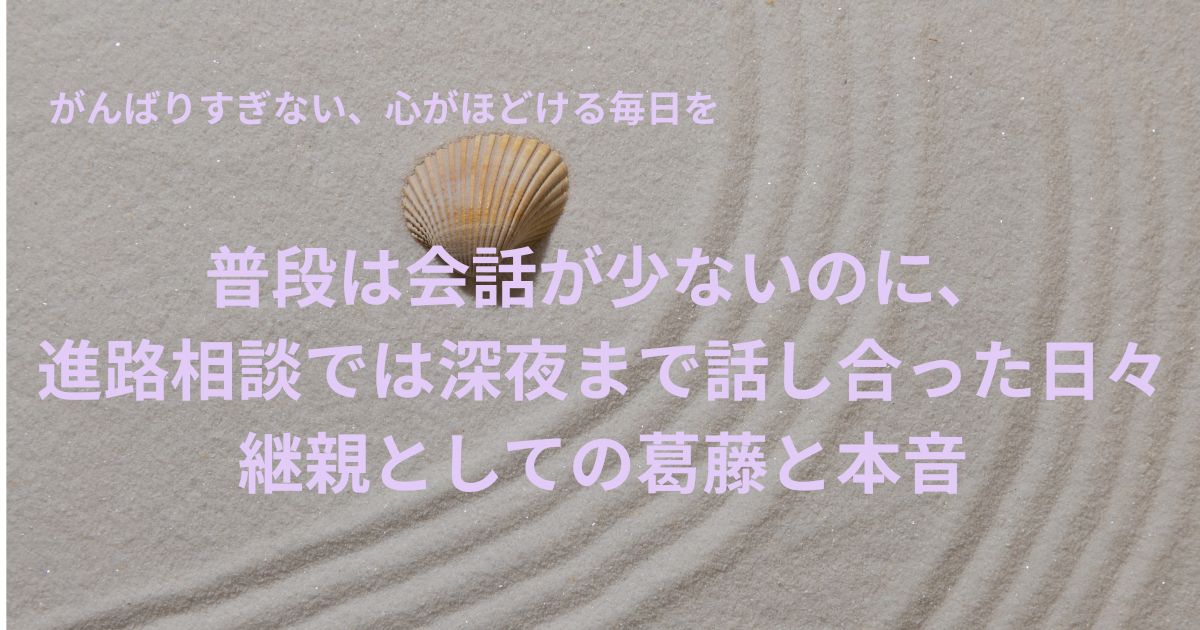
普段、私と子どもの会話はあまり多くはありません。
ステップファミリーとして共に暮らしてきましたが、どうしても必要最低限のやり取りが中心になりがちです。
一方で、家族全体の会話や、妻と子どもの会話はとても多く、にぎやかに過ごす時間も多いのが我が家の特徴です。
だからこそ、私自身が子どもとどう関わるかは常に悩みどころであり、課題でもありました。
ただ、不思議なことに「進路相談」のように人生の大きな岐路に立つときには状況が一変します。
普段は少ない私と子どもの会話も、その時ばかりは一気に濃くなり、夕飯後の20時頃から深夜0時を過ぎるまで話し込むこともありました。
子どもが「自分で考えない」ことへの不満
私から見て子どもに強く不満を感じたのは、自分で考えて行動しようとしないことでした。
小さい頃から最終的には妻が「これをしなさい」「あれをしなさい」と指示を出すことが多く、
その結果「言われたことをやればいい」という習慣が身についてしまったように思います。
さらに本人自身も「自分は考えるのが苦手」と思い込んでいる部分があり、
主体的に動くことを避けてしまう。
その姿を見ていると、どうしてもイライラが募りました。
特に高校や大学といった進路を選ぶ時期には、
「どうしてもっと自分で調べないんだ」「考えようとしないんだ」と強いストレスを感じました。
英語に強い高校を希望した子ども
中学時代、子どもは英語が比較的得意でした。
そのことから「将来は英語を使った仕事をしたい」と言い出し、英語教育に力を入れている高校を希望しました。
最終的にその学校を選んだのは子ども本人です。
ただ、私と妻は内心反対でした。
理由は単純です。学力的に少しレベルが高すぎると思ったからです。
親が反対した理由
中学の狭いエリアで多少成績が良いぐらいでは、広い地域から集まる私立高校のレベルには届きません。
しかもその学校には、帰国子女や、親が英語圏の国籍を持つハーフ・クォーターの子が多く集まります。
そんな環境でやっていくには、相当な努力が必要です。
けれど、子どもは中学校の成績に自信を持ちすぎていて、親の忠告には耳を貸しませんでした。
「無理だ」「やめた方がいい」と頭ごなしに否定はせず、危険性を繰り返し説明しましたが、
結局は子ども自身がその高校を選択しました。
想定通りの結果
結果は、正直「案の定」でした。
入学してしばらくは頑張っていましたが、1年の夏休み頃には挫折。
すっかり英語嫌いになってしまいました。
それでも、不登校になることなく卒業できたのは幸いでした。
友人関係や学校生活自体は楽しめていたようで、そこは救いだったと思います。
ただ、「努力すれば乗り越えられる」という私たちの期待は外れ、
本人も「やっぱり無理だった」という現実に直面することになりました。
深夜まで続く話し合いと説教
進路の話し合いは、時に深夜まで及びました。
「どうしたいのか」「何を目指すのか」と問いかけても、子どもはなかなか答えません。
結局、こちらがいろいろな具体例を出して説得する形になり、
気づけば説教のような雰囲気になってしまうことが何度もありました。
私はできるだけ感情的にならないよう、理論的に話そうと心がけていました。
しかし、どれだけ言葉を尽くしても、子どもの心には響いていないのが分かるのです。
それでも「本人のやる気を奪わないように」と思い、希望した高校を受験させました。
勉強しない子どもへの苛立ち
ただ、受験勉強の過程では私のイライラが爆発することも多かったです。
- 合格が危ういのにゲームに夢中
- スマホに時間を費やすばかりで勉強に集中しない
- 塾に通っても成果が出ず、最終的には個別指導をつけることに
「自分で決めた高校なのに、なんで努力しないんだ!」
「遊んでいる場合じゃないだろ!」
そう何度も強い口調で説教しました。
今思えば、私自身もやるべきことを先延ばしにしてしまう人間なのに、
子どもには完璧を求めすぎていたのかもしれません。
でも、それが「我が子」ではなく「継子」だったからこそ、
余計にイライラが強く出てしまった部分もあると思います。
想像以上に残った“しこり”
最終的に子どもはなんとか合格し、無事に高校生活を送ることができました。
けれど、この一連の経験は私の中に大きなしこりを残しました。
- 「どうしてもっと自分で考えられないんだ」
- 「あれだけ話し合ったのに、結局伝わらなかった」
- 「やっぱり血のつながりがないからなのか」
そうした思いが、その後の私の行動や感情にも影響を与えている気がします。
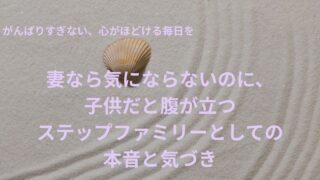
まとめ ― 話し合いの意味
普段の会話は少なくても、進路のような大事な話では時間を惜しまず向き合った。
それは間違いなく、親としての責任感からでした。
けれど、「伝わらなかった」「響かなかった」という虚しさや苛立ちは、
いまも私の心に残っています。
それでも、頭ごなしに否定せず、子どもの選択を尊重したことは、
少なくともひとつの「正解」だったのかもしれません。
結果がどうであれ、一緒に考え、悩み、時には説教もして向き合った。
それが家族としての歩みだったのだと思います。