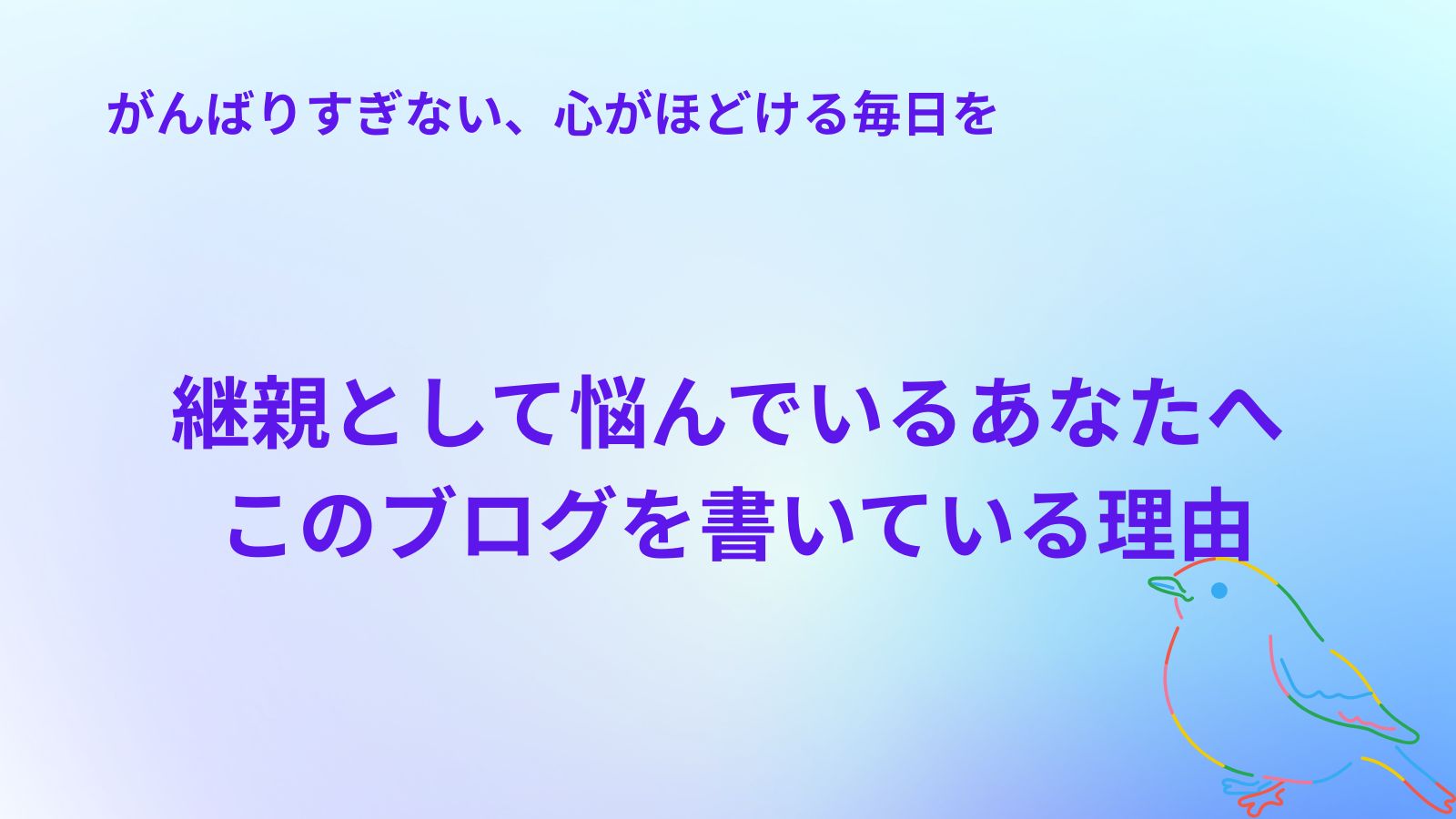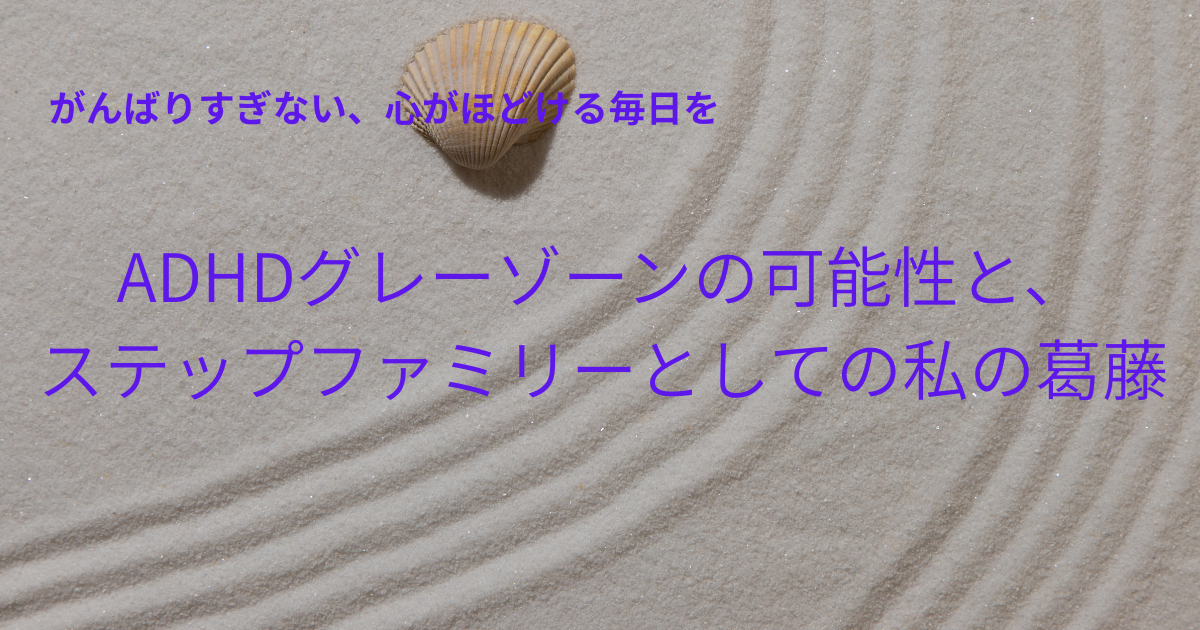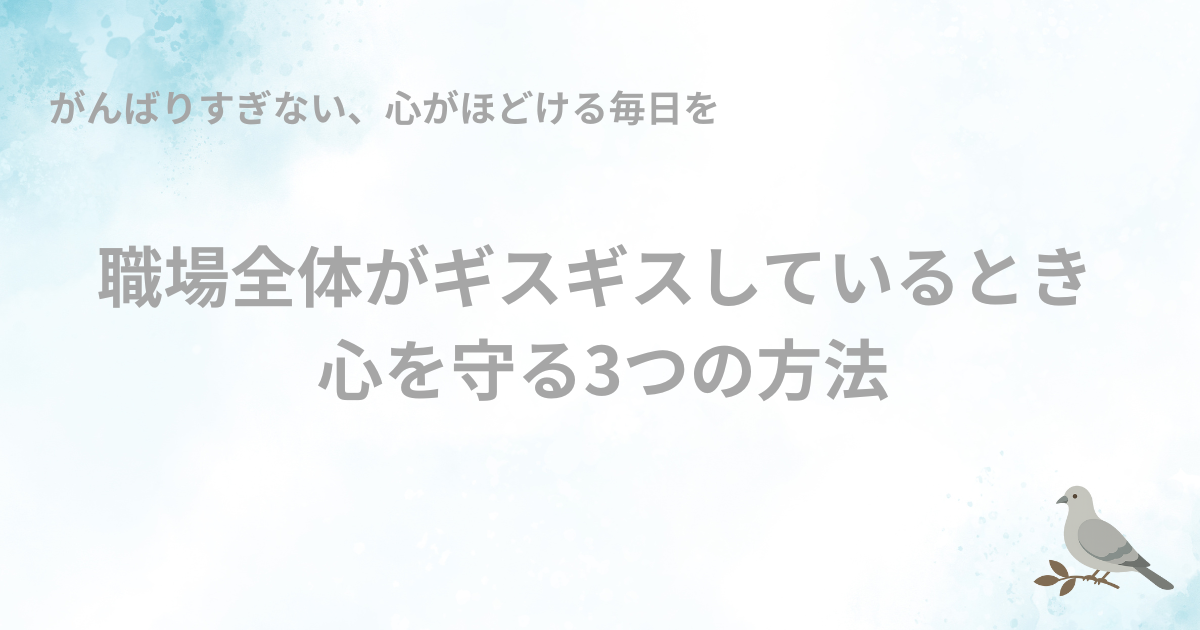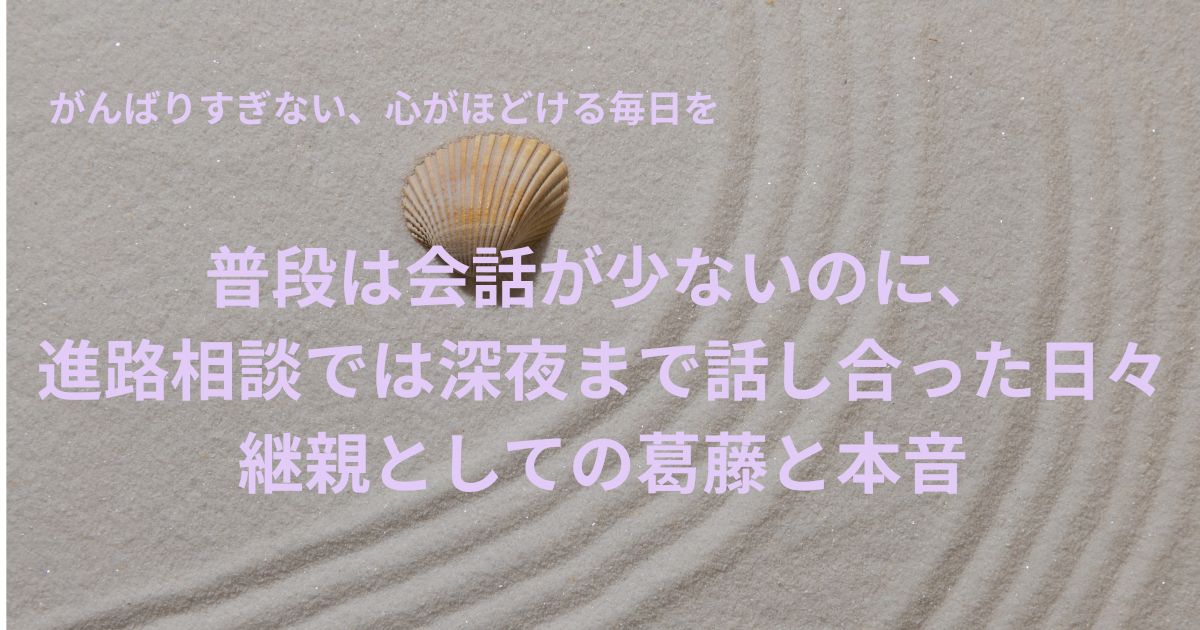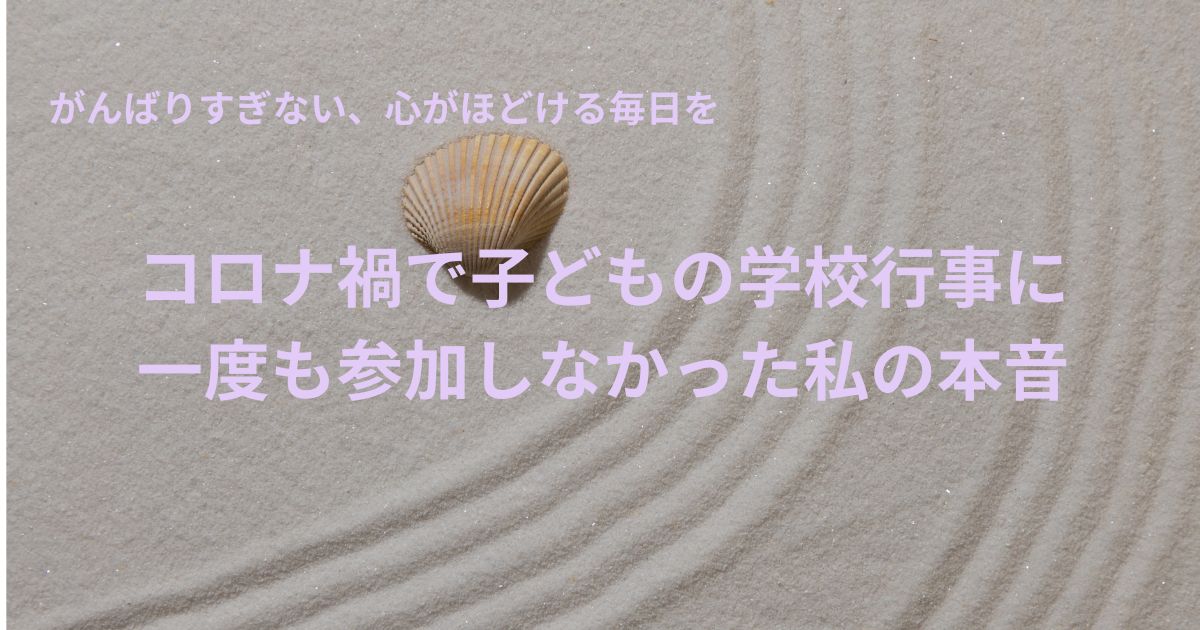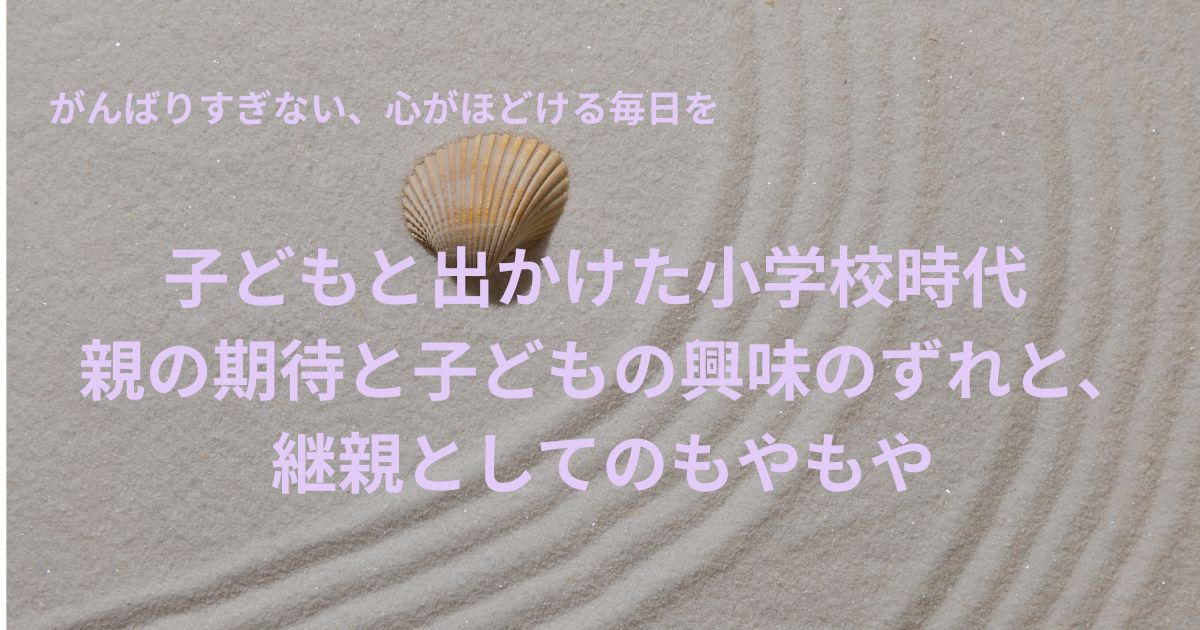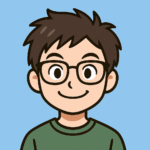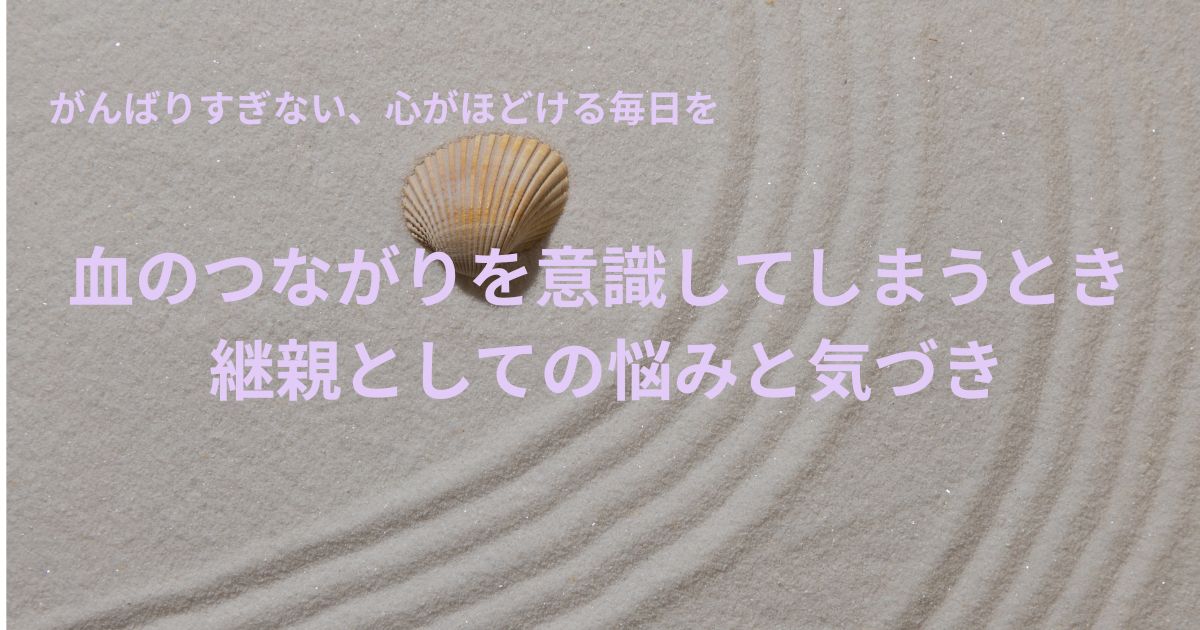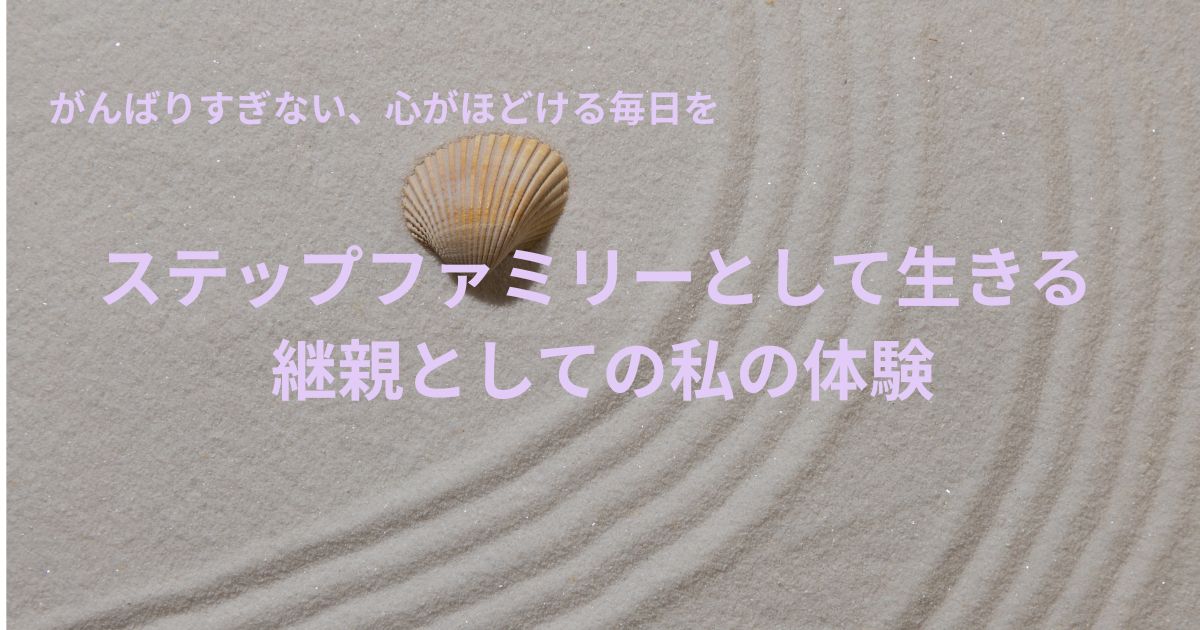ADHDグレーゾーンの可能性と、ステップファミリーとしての私の葛藤
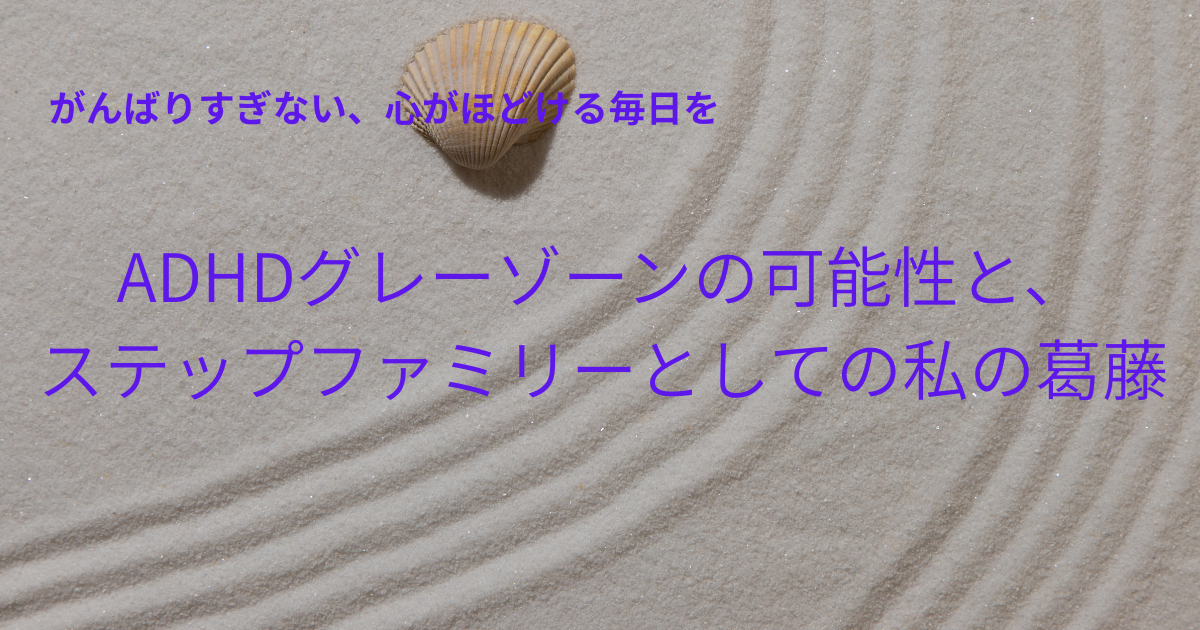
はじめに
妻と結婚してステップファミリーとして暮らし始めてから、私は「ADHDグレーゾーン」という言葉を意識するようになりました。
子どもがその可能性があると妻から聞いたのです。実は妻自身にもそういう傾向があるかもしれない、という話もありました。
正直、それまで私はADHDについて全く知識がありませんでした。初めて聞いたときから少しずつネット記事などを読み、理解を深めようとしました。
ADHDグレーゾーンとは?
ADHD(注意欠如・多動症)の特徴が一部当てはまるけれど、診断基準を満たすほどではない状態を「グレーゾーン」と呼ぶことがあります。
忘れ物が多い、勘違いが多い、注意力が散漫になりやすい――そうした傾向は日常生活の中でも目立つことがあります。
ただ、「障害」というよりは個性や癖の範囲にも見えることが多く、判断や対応がとても難しい。
私も暮らしの中で「ああ、これはそうかもしれない」と感じることが多々ありました。
一緒に暮らす中で感じたストレス
最初に強いストレスを感じたのは、一緒に暮らし始めた頃です。
勘違いや忘れ物が頻繁に起こり、そのたびに「なんとか直さなければ」と必死になりました。
- 「それだと今後困るだろう」
- 「今のうちに矯正しないとダメだ」
そう思って、繰り返し注意しました。
けれど、改善されることはほとんどありませんでした。
ストレスはどんどん積み重なり、あるときには肌荒れがひどくなり、皮膚科に通うほどになったこともあります。
それまで肌トラブルとは無縁だったので、自分でも驚きでした。
考え方を変えるようになったきっかけ
時間が経つにつれて、私は考え方を変えるようになりました。
- 忘れ物 → いくら親が注意しても治らない
- 勘違いの多さ → 本人が大きくなってから自分で対処するしかない
そう割り切るようになったのです。
結局のところ、自分だって忘れ物をしたり勘違いをしたりすることがあります。
違うのは、その頻度が多いか少ないかだけ。
「困るのは本人。だったら自己責任として経験から学んでいけばいい」
そう思えるようになったことで、以前ほど強いストレスを感じることは減りました。
血のつながりか、ADHDグレーゾーンか
私の悩みをさらに複雑にしたのは、「血のつながり」という要素です。
- 「子どもを理解できないのはADHDグレーゾーンだからなのか?」
- 「それとも、実の子ではないから共感できないのか?」
そう自分に問い続けた時期がありました。
けれど、今振り返るとそれはあまり意味のない問いだったのかもしれません。
忘れ物や勘違いは「個性」であり、誰にでもあるもの。
そこに「血のつながり」を持ち込んでしまうと、余計に関係が苦しくなるだけでした。
今の私が思うこと
いまでも解決方法が見つかったわけではありません。
ADHDグレーゾーンという言葉にどう向き合えばいいのか、完全な答えは出ていません。
ただ、以前のように「直さなければ」「矯正しなければ」と思うことは減りました。
それよりも、「一緒に暮らす中でどう折り合いをつけるか」が大切だと感じています。
妻と子どもの関係を見ていると、忘れ物や勘違いも含めて「その子らしさ」として受け止めている部分があるように思います。
私はまだ完全にそうはできないけれど、少しずつ「受け流す」「深く考えすぎない」ことを覚えてきました。
まとめ
ADHDグレーゾーンの可能性は、診断が難しく、対応方法も人によって違います。
「個性」として受け止められる部分もあれば、生活の中でストレスを感じる部分もあります。
ステップファミリーという立場ゆえに、「理解できないのは血のつながりがないからなのか?」と悩んだこともありました。
でも今は、**「誰にでも忘れ物や勘違いはある」**というシンプルな事実に立ち返るようにしています。
完璧な親子関係はなく、完璧な対応もありません。
大切なのは「無理に直そうとせず、一緒に暮らしながら折り合いを探すこと」。
それが、私がこの経験から学んだ一番の気づきです。